はじめに
10月26日(日)に、アーネスト・カーツの著書 『Not-God – A History of Alcoholics Anonymous』の日本語訳『Not-God』の第3回スタディ・ミーティングを開催しました。
今回の焦点は、「AAやGAは表面的には宗教を避けているが、本質的には宗教的なものである」というものでした。
つまり、AAやGAが「宗教」という語を慎重に避けながらも、実際には深い宗教的構造をもっていること。
そして「霊的(spiritual)」という言葉が選ばれた背景には、近代社会との緊張関係や、実践上のリアリティがあることを探りました。
AAやGAが目指すのは、教義や信条としての宗教ではなく、実践を通した生きた霊性です。
その意味で、プログラムとは、頭で理解するものではなく、日々の体験を通して確かめられていくものなのだと感じます。
そのうえで、今回は「知識」を語るのではなく、「自分の経験」をもとに話すことを意識しました。
参加してくださった方々にも問いかけながら、それぞれが考えるきっかけとなるようなミーティングになるように進行したつもりです。
ただ、ミーティングの後にはいくつかの率直なフィードバックもありました。
たとえば、「近代が重視する理性の限界にはもっと踏み込めたのではないか」「GAとのつながりがわかりにくかった」といった意見です。
自分のいたらなさを感じながらも、次にどう生かしていけるかを考えていきます。
次回のNot-Godスタディは11月30日(日)21:00からの予定です。
ここからは、毎月水曜日のミーティングで考えた「祈り」について、私自身の経験を交えて書いてみたいと思います。
自分の経験
これまでのミーティングでは、「夜の祈り」「朝の祈り」「決められないときの祈り」と、さまざまな場面での祈りについて話してきました。
今回はそのまとめとして、祈りの本当の目的について、私自身の経験を通して考えてみます。
まず、ステップ11で語られる「祈り」と「黙想」の基本的な意味を、改めて整理するとこうなります。
- 「祈り」とは、自分の望みを叶えてもらうお願いではなく、神の導きを実際の行動に移せるよう助けを求めること。
- 「黙想」とは、ただ考えを巡らせることではなく、神の声に耳を澄まそうと心を開く、能動的な姿勢。
頭ではわかっていても、実際にそれを日々の生活で実践できているかと問われると、なかなか胸を張れません。
夜は子どもを寝かしつけながらそのまま寝てしまうことが多い。
でも、朝は5時前に起きて静かな時間をもち、祈りの言葉を口にしています。
仕事でトラブルに直面したときや、心がざわついたときにも、そっと祈ることがあります。
それでもなお、「祈りと黙想を実践できている」と言い切るには、どこかためらいが残ります。
正解を知ろうとする
最近、はっきり気づいたことがあります。
私は何か行動する前に「正解を知りたい」と強く思ってしまう。
つまり、結果を自分でコントロールしようとしているのです。
言い換えれば、自分が神のようにふるまってしまっているということ。
私の苦しみの多くは、たぶんこの姿勢から生まれていました。
けれど、私たちに求められているのは「神のように完璧になること」ではありません。
ただ、現場に出ていき、責任を果たし続けること。
そして、自分に望まれていることを一つひとつ実行していくこと。1
それだけなのだと思います。
だから、私の祈りに足りなかったのは「どうすればうまくいくか」という答えを求めることではなく、たとえ結果がわからなくても
「私が行きます」と言える姿勢。
そのうえで、自分にできることを行い、結果を委ねる。2
そこに、祈りの本質があるのかもしれません。
それは、神を動かすための祈りではなく、自分を明け渡すための祈りです。
おわりに
これまでこのブログでは、ステップの解説を中心に書いてきました。
でも最近は、少しずつ自分の体験を通して語る方向へシフトしています。
うまくいかないこともありますが、誰かの役に立つのは、完璧な説明ではなく、自分の正直な姿を見せることなのかもしれません。
これからも、祈りや実践の中で気づいたことを分かち合っていきたいと思います。
次回、10月12日(水)のミーティングではステップ12を取り上げる予定です。
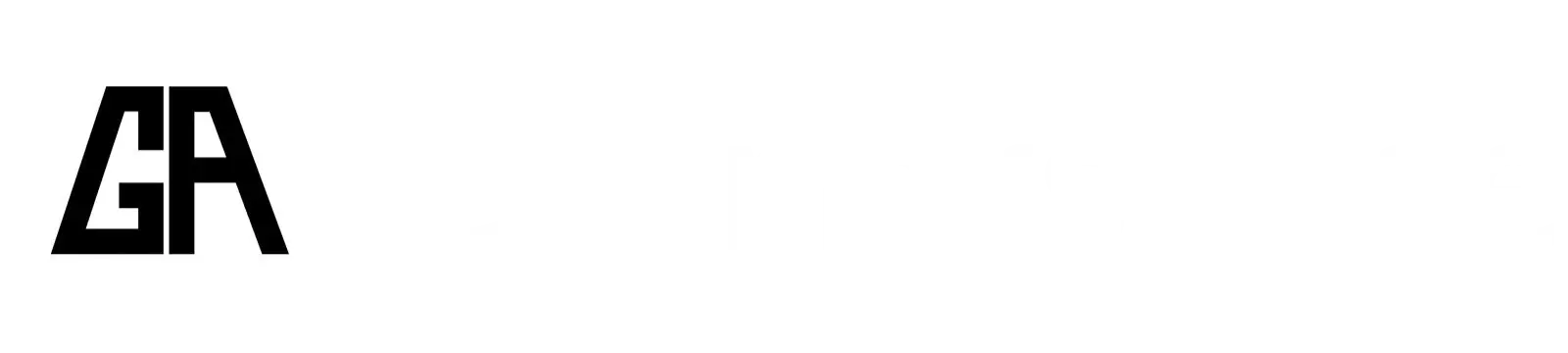
コメント