はじめに
今月のミーティング後の雑談タイムでは、年末年始はスリップするメンバーが多くなるという話題になりました。たしかに、年末年始は職場や友人の集まりなどでもギャンブルの話題が増えてきます。
私自身はというと、職場や友人にはGAメンバーであることは言っていませんので、ギャンブルの話題にはなるべく加わらないか、適当に話を合わせてやり過ごしています。個人的にはあえて言う必要はないとは思っていますが、GAメンバーということがオープンであれば、面と向かってギャンブルの話を聞いたり発言する必要はなくなるのかもしれません。難しいところですが、ギャンブルの問題のことを知らない人に対して、あえてオープンにするかは個々の判断になってくるのでしょう。
さて、あいかわらず、ステップ6とステップ7の続きです。
原理はシンプル、実践は困難
私たちは生き方の原理を見つけようとしているのである。原理というのは普遍的で変化しないものだ。人生はこの生き方の原理にもとづいている。1
生き方の「原理」とはいったい何でしょうか。
それは、前回みてきたように「古い考え」を捨て「新しい考え」をすること、すなわち神の意志に基づいた生き方をすることです。これまで、私たちは自分の意志に基づいてあらゆることをコントロールしようと生きてきたわけですから、それを手放せばよいのです。
しかし、今まで自分の力に頼った生き方をしてきた私たちが、すぐに原理にもとづいた生き方をしていくことは簡単ではありません。では、なぜこのシンプルな原理がなかなか実行できないのでしょうか。
ところで、宗教も同様の原理をもっているが、1000年以上ものあいだそれに多くの指示や解釈を付け加えてきた結果、いまや宗教のプログラムから原理を見つけ出すのは簡単ではないように思う。また、別の問題に巻き込まれ、生き方の基本原理から遠ざかってしまった宗教集団もある。2
宗教ではしばしば、原理を守るために、組織化して教義をつくり、儀礼や制度を整えて形式化していくというこがおこなわれます。これは、宗教の教えが広まっていく過程で必要なことなのかもしれませんが、見方を変えれば、異説や異端が出ないように物事をコントロールしようとすることの表れです。
古今東西を問わず、たとえば、キリスト教では宗教改革によりカトリックから分離してプロテスタントが生まれ、日本でも旧仏教の中から鎌倉仏教が生まれた過程をみればそのことがよくわかるのではないかと思います。本来は神の考えに基づいて生きていくのが宗教の教えであるにもかかわらず、人間が考えたルールに基づいたものになってしまっていることがしばしばあるのです。
ジョー・マキューは、ここでは宗教のことだけを書いていますが、GAでも同じ状況になってはいないでしょうか。
私たちギャンブラーは白黒思考をしがちで、人から認められたいという欲求をもっています。そうすると、自覚はしていなくても、すべてを完璧にすることを目指してしまいます。だから他のメンバーやグループの考えや行動が気に入らないと、自分たちのやり方に従うようにコントロールしようとしてみたり、伝統(一致のためのプログラム)を持ち出して裁こうとしたり、あるいは無視を決め込んだりしてしまいます。これは、共同体の中だけでなく、仕事や家庭、日常生活でも同じです。
しかし、私たちは、神ではないのですから、すべてを完全に思いどおりにすることなど決してできません。私たちはずっと不完全なままなのです。宗教の歴史が証明しているように、「成長」ではなく「完成」を目指すと、神の意志に基づいた生き方をするという原理から遠ざかっていってしまうのでしょう。
根本の問題
強迫的な行動やアディクションがどのようなものであれ、それは根本にある病気の症状にすぎない(自己中心に生きるなら、欲望につかまる。欲望にはきりがない!)。しかし、プログラムを使えば、強迫的な行動を克服することができる。プログラムは根本の問題に取り組むからだ。3
何度も繰り返しになってしまいますが、根本にある病気とは、神の考えではなく自分の考えにもとづいて生きていこうとすることです。ビッグブックでは、これを「霊的な病」4と呼んでいます。
また、ここでは「強迫的な行動を克服することができる」と書いてありますが、精神の強迫観念(狂気)と身体のアレルギー(渇望)がなくなるわけではありません。
私たちがプログラムに取り組む目的は、ギャンブルをする前に起こる強迫観念や、ギャンブルをやった後に起こる渇望がなくなって、安全にギャンブルができるようになることではなく、古い考えを捨てて新しい考えにもとづいた生き方を実践していくことです。
私たちは不完全な人間なのですから、完璧に神の意志に基づいた生き方を実践することはできないと思います。しかし、その方向に向かって取り組んでいくことができれば、あのギャンブルで苦しむ生活に戻ることはないでしょう。
おわりに
この連載のトピックは二つに絞りましたが、ミーティングでは「愛」や「反応」、「自分自身に対する関心」などについて活発に意見交換がされました。やはり、ミーティングは一方通行ではなく、参加者してくれるメンバーとの双方向のやり取りが必要だと思います。
自分の発言が間違っていたり、的外れであることを気にする必要はありません。自分の考えをアウトプットしていくことで、理解が深まっていきますし、他の参加者の役にも立つのです。
グループとしても参加してくださる方の役に立つ運営を目指していきますので、引き続きよろしくお願いします。
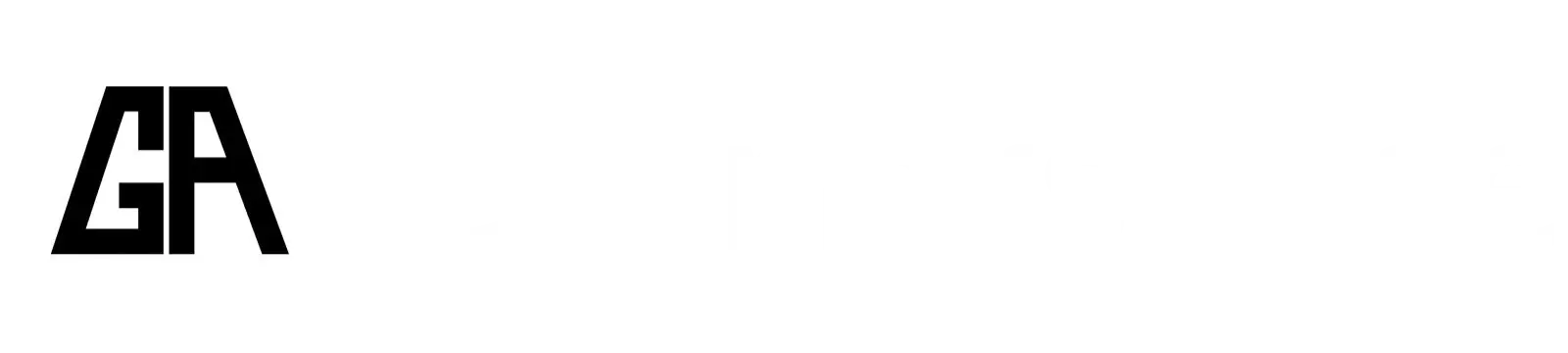
コメント